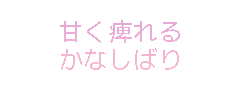(それは綺麗な琥珀色で、光の屈折を織り交ぜてはキラキラ輝いているのでした、)
彼の手によく馴染んだロックグラスは、やはり彼女のその小さな手のひらにはあつかわしくないようで、落とさないように両手で持って傾けると、角が取れて歪な形になった氷がカランと涼しい音を立てた。グラスについた細かい水滴の粒をキュ、と指で擦ると、途端に鮮明な色彩が目に飛び込んで来る。その美しさに思わず目をしばたかせた。琥珀色のウイスキーが放つ、甘くて癖のある独特の香り。それだけで、酔ってしまいそうだった。
「おいしいのかな…」
いつも表情に何の感慨も見せず、ただ静かにこれを呷っている彼だが、日々愛飲しているのだから、それなりに好きではあるのだろう。くん、再度匂いを嗅いでみても、何だか口を付けるには躊躇われる香りが、ただ鼻をくすぐるようにするだけだった。一方で、いったいこれがどんな味をしているのか、という興味は確かにあった。甘いのかもしれないし、反対に、とても苦いのかもしれない。宝石のように輝く綺麗な色が、キラキラと瞬いては少女の唇を誘っていた。
(せっかくお祝いに来たというのに、)
(彼の姿がどこにも見当たらないの)
何故だか最近、妙に酒に弱くなったような気がする。以前なら、考え事をするときには欠かせなかったはずのそれも、今となっては頭の中で何か少し物事を巡らせただけでいよいよ調子が狂うのだ。とにかく、近頃は酒を呷るくらいしかすることがない。酒の度数に対して、摂取ペースが速すぎるのかもしれない。…それを咎める者が居ないのも、まず問題だ。否、誰も止めようなどとは思わないのだろうが。
(今日は、あのくだらねぇ祝いの席でも酒を飲んだからか)
とにかく、酔いの回った情けない姿をあの場で晒すわけにはいかなかったわけで。ひとり執務室を抜け出し、ひんやりと風の吹くバルコニーでぐるぐると忌ま忌ましく旋回する思考をどうにか落ち着かせて部屋に戻ったのが今で、…ドアを開けた途端に視界に飛び込んで来た光景に思わず目を見開いた。
「…何してんだ、」
バーボンウィスキーを、ロックで。もちろんストレートで飲むより少しは溶け出した氷で濃度も薄まっているはずだ、が、それでも普段愛飲しているそれとほぼ同濃度には変わりはない。耳たぶまで真っ赤に染め上げたひとりの女が、椅子の上でくたりとしていた。深い色をした大きなふたつの瞳も、今まさに、重たそうな瞼に覆われようとしている。
「、ザンザス…?」
「…飲んだのか」
「…ちがうの…ううん、あの…ちょっとだけ、」
グラスに残された酒の量は、部屋を出る前とほとんど変わっていないような気がする。恐らく本当にひとくち含んだ程度なのだろう。…それにしても、こいつがここまで酒に弱いとは。鼻にかかるような甘ったるい声が、脳髄をびりびりと痺れさせる。酷く眠たそうな声でもあるし、はたまた官能へ誘うような声でも、あった。
「…おい」
「ふあ、眠い…」
「そんなとこで寝るんじゃねえよ、カス」
遂にはうとうとと危なっかしく船を漕ぎ出した少女に、ザンザスは軽く舌打ちをすると、極力見ないようにしていた少女の体へと視線を落とした。アルコールによって僅かに上気したきめ細かい白い肌が、みるみるうちに薄紅色に染まっていく。小さな手も、首筋も、短いスカートからはみ出ている脚も。
「チッ…めんどくせぇな、」
もはや夢の世界へと片足を突っ込んでいる少女の体を軽々と抱き上げると、ザンザスは近くにあるソファへ彼女を移動させようと静かに足を進めた。そのとき、腕の中で、もぞ、と少女が身じろぎをした。
「…、ザンザス…」
「ああ?」
「えっと、…おめでとう。あのね、お誕生日…」
わたし、それを言いに、ここまで来たの。少女はふわりと笑うと、男の胸に頬をすり寄せ、今度こそスウスウと気持ち良さそうに寝息を立て始めた。この日、いったい何度耳にしたかもわからなくなるほどに聞いた、ありきたりな祝いの言葉。それをまた、彼女はこんなタイミングで。
(…くだらねぇ、)
形の良いふっくらした唇が、それ以上言葉を紡ぐことはなかった。ただ、ザンザスは腕の中にの温かくて柔らかい存在が、体中の、それこそ爪先から頭の隅に至るまで、己の全ての感覚を、――
「あらまぁ、やっと見つけたわ!」
バン!と派手に音を立てて開いた部屋の扉から、色鮮やかな筋骨隆々の晴の守護者が飛び込んで来たせいで、全ての思考と煩悩を吹き飛ばされてしまったのは言うまでもなく。
「ベッドから抜け出してどこかへ行っちゃうものだから、心配してたのよ〜!ってあら?ボス、この子、寝ちゃったの?」
「……」
「まさかボスの部屋に来てるとは思わなかったわ…!顔赤くしちゃって可愛いわねぇ〜、もう!」
「…知るか。そこら辺に寝かしとけ」
いよいよ鬱陶しく騒ぎ立て始めたルッスーリアに、スヤスヤと呑気に眠り続けている少女の小さな体をさっさと押しつけると、ザンザスは踵を返して、先刻まで少女が座り込んでいた自分の椅子にどっかりと腰を下ろした。ゆらゆらと光を反射するガラス製のロックグラスを右手で掴むと、ようやく馴染んだ感覚にありつけて、気分が大分落ち着いた。
「ボスったら照れ屋さんなんだから!」
パタン。ドアが控え目な音を立てて閉まると、カラン、とグラスを傾けて口に運ぶ、が、
突如として脳裏に、艶めかしいあの桃色の唇が鮮やかに、蘇った。
(…別に何も、めでたかねぇんだよ)
鮮やかな琥珀色が、甘く癖のある匂いが、何故か今、この時ばかりは、男がグラスに口を付けるのを、確かに躊躇わせていた。
小さくなった氷がじわりじわりとその存在を、琥珀色の中へ溶かして消えてゆくのを、ただ見つめることしかできずに、