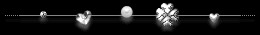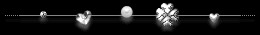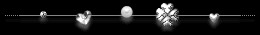朝焼けの館
□桜の愛し君
1ページ/8ページ
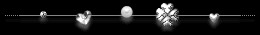
この気持ちを自覚したのは、いつの時だったろうか。
それは、一目見たその時から解けていたのかもしれない、柳蓮二という方程式。
その姿を見かけたのは、まだ中学に入る前の事。
日本人形のように切り揃えられた髪の、喩えが悪いが座敷わらしのような少女。
フェンス越しのその姿は、まるで芍薬の愛らしさだった。
俺らしくもなく、話しかけて言葉を交わしたい衝動に駆られたが、あの綺麗な瞳を曇らせたくはないと、帽子を被りなおすだけだった。
そして四月―――。
中学の入学式で、桜の下…目にしたその姿は、ブレザーにズボン。
紛うことなく、男の姿だった。
「あっはっは、馬鹿だね真田」
目の前で菓子を広げ齧りながら、笑うは幸村。
線の細い、女子と違えるような容姿からは想像もつかない、テニスのパワープレイヤーでもある。
それは俺も出場したジュニアの大会で、優勝した実績も伴う。
「あいつ、有名じゃないか。ダブルスの大会で優勝した柳」
「噂には聞いていたが…あんな可憐な姿からどう想像しろというんだ。お前の口からダブルスと聞いた時も、俺はてっきりミクスドかと」
眉間の皺を深くした俺を、軽くため息をつきながらもう一度、お前は馬鹿だ、と前置きして続ける。
「俺が女の子の話をするわけないじゃないか。ああごめん、可愛くない方は覚えてない」
ばっさりとそう切り捨てる幸村の口の悪さには少々辟易したが、蓮二を可愛いと称するのは悪くないと思った。
白い肌に伏せた瞳の長い睫毛。
さらさらとした髪は風に揺れ、桜色の唇を彩る。
同じクラスとなり、男だと知った今でもその一挙一動に魅かれている自覚はあった。
その感情に名をつけるのが怖くて、幸村にもこの気持ちは話せずにいる。